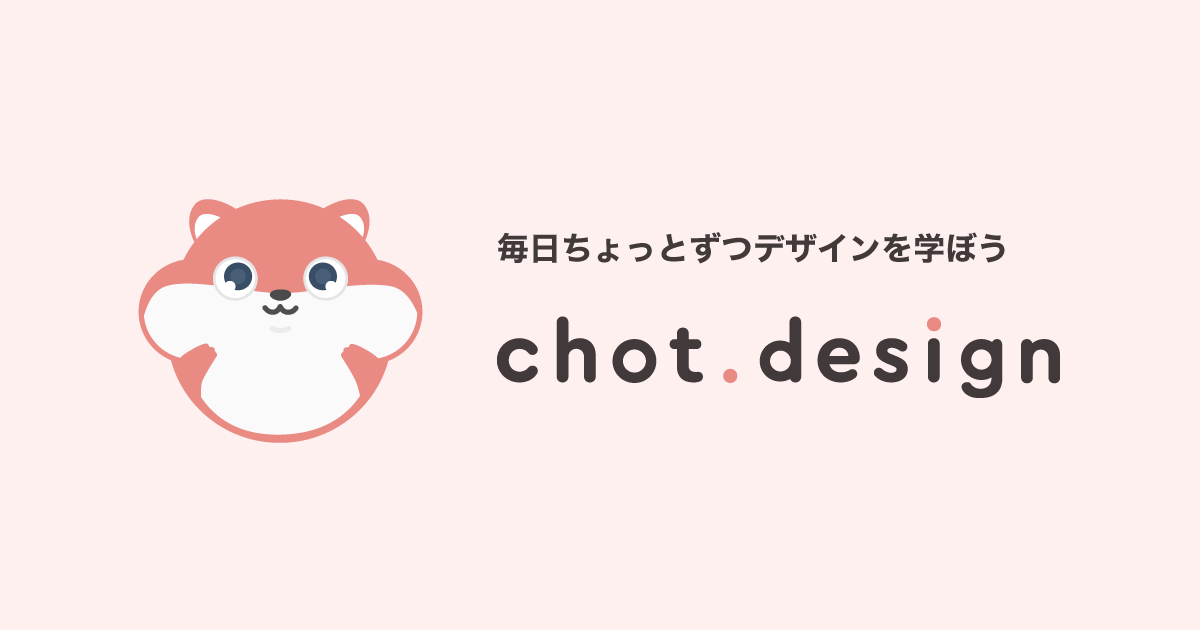いよいよ10月10日に公示が迫った衆議院議員総選挙。小池新党に続いてギリギリで枝野幸男氏による立憲民主党の結成が発表されました。
2013年に公職選挙法が改正され、インターネットを利用した選挙運動が解禁。そして今回は2014年12月以来となる総選挙です。ネット選挙が解禁されて以来2度目の総選挙を、候補者たちはどのように戦っていくのでしょう?
10月2日に結成したばかりの立憲民主党のここまでのネット選挙対策についてまとめました。
目次
ネット選挙とは?
まずこの記事内で使う「ネット選挙」という言葉について認識合わせをしておきます。ネット選挙とは「インターネット選挙運動」の略称で各所では使われています。ネット選挙のことはつまりインターネットを使った候補者や党の宣伝活動を指します。なので「ネット投票」とは違った意味で使われます。
日本では2013年4月に公職選挙法が改正され、インターネットを利用して選挙運動が出来るようになりました。具体的にはウェブサイト・ブログ・掲示板・SNS・動画の共有や中継サービス上で宣伝活動を行うことが出来るようになりました。条件として各コンテンツ上には連絡先となる電子メールなどの記載を行うことや、18歳未満の選挙運動の禁止などがあげられます。(例えば未成年が候補者のツイートをリツイートするなどの行為は禁止されています)
それまでビラ・ポスター・街頭演説・選挙カーなどで行われてきた選挙活動ですが、ネット選挙解禁後は候補者がリアルタイムで情報を発信できたり、有権者と双方向のコミュニケーションを取ることができるなど、2014年の総選挙では候補者の投票行動に大きく影響を及ぼしたという調査結果もあります。
前回の総選挙から3年、インターネットの利用環境はPCや携帯電話からスマートフォンへと大きく移り変わりました。前回の総選挙はネット選挙解禁後初の選挙であり、今回の総選挙はスマホ時代初の選挙ということになります。さらにスマホの普及の波に乗ってともに成長したのがSNS。LINE・Twitter・Facebook・Instagramなどが一般的となった今だからできるコミュニケーションが、今回の選挙の結果を大きく左右する可能性があります。
枝野幸男氏とインターネット
枝野さんは民主党時代に起きた未曾有の大震災3.11のときに内閣官房長官として記者会見の対応を行っていました。昼夜を問わず記者会見に不眠不休で真摯に対応する姿を見たツイッター民たちが「枝野寝ろ」「#edano_nero」とつぶやきました。実際に震災が発生してから数日の睡眠時間は1日1〜2時間だったそうです。
また今年の4月には分散型SNS『マストドン(Mastodon)』の「friend.nico」インスタンスに「えだのん」名義で登場。マストドン上で『ニコニコ超会議2017』に来場したことを投稿し、ユーザーたちを驚かせました。もともとアイドル好きという一面がマスコミなどでも報道されていた枝野さんですが、最新のSNSを試してみるなど、インターネット事情についてはよく研究されていたようです。
「枝野寝ろ」や「マストドン」などを通じて、枝野さんはSNSにおける小さな気づきや成功体験を積み重ねていたのかもしれません。
ロゴを一晩で作った話
さて、立憲民主党を公示まで10日を切った10月2日に結成した枝野さん。はじめに取り掛かったのは新党発表の記者会見の準備と、そこで発表するロゴの制作だったのではないかと考えられます。

政党のロゴはデザイナーの方が一晩で制作したもの、ということで報道がされています。
立憲民主党のロゴに注目集まる デザイナーが一晩で作成、「民」の字が大きいのにも意味が
太く、力強く、そして民主党の「民」がより強調されたこのロゴ。
記者会見と同時に、このロゴをアイコンにしたTwitterアカウントが開設され、そのアカウントは常識破りのスピードでフォロワーを増やしています。
希望の党を圧倒的に引き離し、自民党にも迫るTwitterのフォロワー数
10月2日に公開された立憲民主党のTwitterアカウントは一晩で5万人のフォロワーを獲得。その後、10月4日には10万人を突破。たった2日で10万人のフォロワーを獲得するに至りました。
対する希望の党のフォロワー数は10月4日現在で4000にも満たず、この記事を書いている数時間後にはおそらく自民党のフォロワー11万人も軽く超えてしまうでしょう。とにかく同じ政党の公式アカウントとは桁違いのスピードでフォロワーを集めています。
立憲民主党のTwitterアカウントの運用には3つの特徴があります。
1つ目は、「#枝野立つ」。という震災時の「枝野寝ろ」をもじったハッシュタグ。ここ数日Twitter上でつぶやかれていた「#枝野立て」のアンサーとなるこのハッシュタグを多くのツイートにつけています。そしてこのハッシュタグを元にツイッター上では拡散が広がっています。
2つ目は、リプライ対応。立憲民主党宛のツイートを拾っては細かいリプライを行っており、有権者との双方向のコミュニケーションを行おうとしています。これは枝野さんが有権者の声を拾い上げたいという思い、そしてボトムアップ型のリーダーシップを実現したいという思いを、スタッフが汲み取って実行されているのではないかと考えられます。
3つ目は、マスメディアの報道や個人ブログなどを拾ってツイートしているという点。自民党のアカウントを見てみると、自民党公式サイトの記事をツイートしているものしか見当たりません。立憲民主党のアカウントは各社のWebメディアの記事をツイートしたり、個人の方が書かれた街頭演説の全文書き起こしまでツイートしています。これは民進党でも行われていなかったことです。ただ、立憲民主党は公式サイトの公開が行われていないため、このような対応がなされているのかもしれません。
Twitterに続いてFacebookページの活用も
Twitterに続いて10月4日にはFacebookページの運用もはじまりました。こちらは1日でいいね数を1万以上、フォロワー数を1.4万人獲得しています。自民党のFacebookページのいいね・フォロワー数は2400ほどなので、その数は圧倒的です。Twitterほど頻繁に投稿はされていませんが、投稿によってはシェア数1000を超えるものもあり、エンゲージメントは相当高い数値を叩き出しているのではないかと思われます。
スマホ最適化された動画の投稿について
枝野さんは10月3日に有楽町で街頭演説を行いました。その様子は個人の方が撮影されており、YouTube上でも見れるようになっています。そしてスタッフの方が撮影したと思われる動画が、10月4日にTwitterとFacebookページで投稿されました。
決して画質は良くなく、演説のカットをつなぎ合わせたものですが、逆に生々しくメッセージが伝わってきます。音声が悪いためか字幕が添えられているので、サイレントの状態でも動画の内容がわかるようになっており、さらに約1分のダイジェストになっているため、スマホでサクッと見れるようになっています。最近流行りのクラシルやC Channelのようにスマホでの閲覧を意識した長さです。
この動画も一晩で制作されたようです。
公式サイトはいつ公開されるのか?
まだ結成から2日しか経っていないですが、おそらく公式サイトも制作されているのではないかと思われます。政策や公約、所属議員のデータベース、政治献金の窓口など、政党の公式サイトの役割は多岐に渡ります。もしかしたら選挙期間中はソーシャルアカウントの運用に集中して、公式サイトは簡易的なもの(最低でも政策と所属議員一覧)が出されるのかもしれません。
立憲民主党のネット選挙対策は「ソーシャルファースト」
自民党は整った体制があるでしょうし、今からそんなに特別な手段をぶっこんでくるとはあまり思えません。そして小池百合子氏の希望の党のネット選挙対策には戦略PRのベクトルグループが絡んでいるという話です。(小池百合子と希望の党のネット選挙対策、戦略PRのベクトルグループが関与か)
立憲民主党は準備運動なしのぶっつけ本番状態でしょうから、やること・出来ることを絞る必要があります。そんな中で立憲民主党は「ソーシャル」を一番の武器にネット選挙対策を行っています。
Twitter・Facebook・YouTubeなどのプラットフォームを利用すれば、アクセスが集中してもほぼほぼサーバーが落ちるようなこともありません。自前でサイトを運用するとなるとそれなりに保守のコストがかかります。
さらに公式サイトを作ってもGoogleの検索結果の上位に表示されるのにはかなり時間が掛かります。例えば「希望の党」を検索してもWikipediaや選挙報道が検索上位に来てしまいます。この状態はしばらく続くでしょう。今、一生懸命公式サイトを作っても、ユーザーの目にはなかなか届かない。だったらソーシャルで拡散する仕組みを利用したほうが目に止まります。
立憲民主党の「時間がない」「リソースがない」「(もしかしたら)金がない」という制約が、ソーシャルファーストのネット選挙対策手法を生み出し、自民党や希望の党を大きく引き離すネット上での拡散効果を生み出しているのかもしれません。
草の根からの民主主義こそが本当の民主主義
枝野さんは10月3日の有楽町街頭演説で「草の根からの民主主義こそが本当の民主主義」という言葉を使いました。インターネット・スマートフォン・SNSの活用こそが、21世紀ならではの有権者の声を拾う手段になっていくことは間違いありません。枝野さんは「#枝野寝ろ」や「マストドン」を通じて、そのことを実感しているのではないでしょうか?
衆議院総選挙の投票日は10月22日。立憲民主党がここからどのように選挙活動を進めていくのか、目が離せなくなってきました。
関連サイト
|
書き手:小島 芳樹 Webやスマートフォンアプリによるサービスを開発・提供する会社で働いています。 Twitter: @yoshikikoji |
この記事が気に入ったらいいね・フォローお願いします!
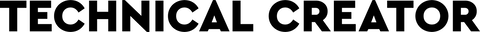
 インスタグラマーmisaさんのネットショップが可愛い
インスタグラマーmisaさんのネットショップが可愛い シャレー渋谷というスタートアップの聖地みたいなマンションについて
シャレー渋谷というスタートアップの聖地みたいなマンションについて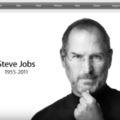 Apple.comの20年間を振り返ろう。懐かしいあの思い出がよみがえる!
Apple.comの20年間を振り返ろう。懐かしいあの思い出がよみがえる! Marvel Studiosのロゴがリニューアル、新たなステージに向かうMARVELの世界
Marvel Studiosのロゴがリニューアル、新たなステージに向かうMARVELの世界 ヌーラボ社がコーポレートロゴをリニューアル。各サービスのロゴも刷新。
ヌーラボ社がコーポレートロゴをリニューアル。各サービスのロゴも刷新。 Sketchおじさんが教えるSketch Togetherを見ながらデザインをトゥギャザーしようぜ!
Sketchおじさんが教えるSketch Togetherを見ながらデザインをトゥギャザーしようぜ! いつかUIデザイナーが宇宙に行く日が来るかも。人工衛星運用ソフトウェアのUI/UXデザイナー募集中
いつかUIデザイナーが宇宙に行く日が来るかも。人工衛星運用ソフトウェアのUI/UXデザイナー募集中 ナルコスの制作費は1話あたり5億円…?!Netflixがアメリカで値上げ。
ナルコスの制作費は1話あたり5億円…?!Netflixがアメリカで値上げ。